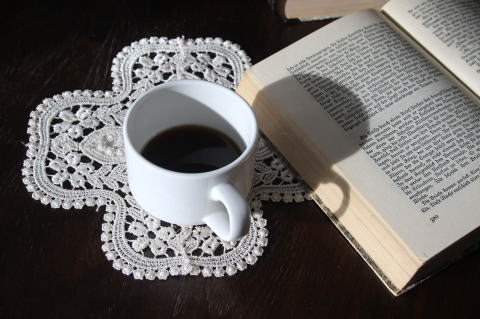憧れのAuthentic HAWAIIそして、いま気になること諸々
- TOP PAGE
- CD&BOOKS
CD & BOOKS
Part 1 「とりあえず今日を生き、明日もまた 今日を生きよう」CD & BOOKS 良い音楽と良い本との出会い
『とりあえず今日を生き、明日もまた
今日を生きよう』
なだ いなだ 著 青萠堂
今回取り上げる著作はなだ いなだ氏の「とりあえず今日を生き、明日もまた 今日を生きよう」というチョッと長く変わった題名の作品です。
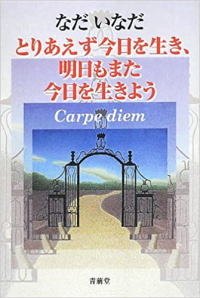 まず、その斬新でユニークな表題に惹かれました。
まず、その斬新でユニークな表題に惹かれました。そして、それにもまして斬新なのが「なだ いなだ」という著者の名前。
こちらは勿論ペンネームで、本名は堀内秀(ホリウチ シゲル)。
「なだ いなだ」とはスペイン語で、nada y nada「何もなくて、何もない」という意味らしい。
2013年の6月に亡くなられているため、残された作品等でしか氏の人となりを辿れないが、私が思うに、ユーモアに溢れていて、ブレることのない筋の通った人だったのではないかということ。
また、冗談なども表情を変えずに何気なくサラッと会話にまじえる、いわゆるシニカルさも持ち合わせていたのではないかと勝手に想像しています。
ところで、本書は2006年から2012年ごろまでに月刊JTUなどに寄稿した原稿を、テーマごとにまとめたものです。
そして、驚くことに青萠堂からこの本の第一刷が発行されたのが2013年6月21日とのことですから、氏の死後僅か10日ほどしか経っていません。
本書の発売に至る経過は、出版社の「青萠堂」からの提案だったことが、ハッキリと「まえがき」の冒頭に書かれています。
ですから、この本の出版に関しては偶然だったのか、予期されてのことだったのか、とても微妙に感じます。
◆
ウィキペディアによると「自身のブログの6月6日付にて自身の体調について記述しているのが絶筆とされる。」とあります。*引用「なだいなだ ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典」最終更新 2022年3月31日 (木) 04:31
このエピソードからも氏の書くことへの執着心というか情熱は、わたしたちの想像を遥かに超えています。氏の「まだ書ける」、「まだ書きたい」という思いが手に取るように伝わってきます。さぞ無念であったことか。
とは言うものの、氏の文面や、もちろん今回取り上げた作品からもそうした張り詰めた思いが具体的に記されたところは見うけられません。至って平常心で淡々と語られるのがなだ氏の特徴です。
件の著書では「人生」「こころ」「うつ」「老年」など誰にも共通する身近な問題をテーマに「なだ いなだ」節で語られています。
「なだ いなだ」節とは、わたしが勝手につけたもので、誤解のないように。
自分に正直で、決して無理をしないなだ氏の語らい型であり、生き方のことです。
「何もかも遠くなる」の項を読めば氏のそんなところが分かるし、「小林秀雄なんて怖くない」では自分自身を偽ることなく、潔くさらけ出していることが分かります。
そこには、恐れ多くも大先輩である小林秀雄をライバル視するなだ氏がいるかと思えば、一転して大先輩の偉大さを素直に認めるなだいなだ氏がいるなど、読んでいてとても愉快になりました。
良いところはいい、悪いところは悪いと認める姿勢、これって分別のなせる業だと思います。自分を含め是非とも見習いたいところです。
なだいなだ氏はこの本の「まえがき」の最後にこんなことも書いています。
時代の空気を吸ってはくようなリズムの文章がぼくのそれの特徴だ。生きている同時代の人間に、刺激や慰めを与えるモラリストであることが、ぼくの仕事だ。世の中が危険な方向に進むのを何とか防ぐことも、自分の役割だ。永遠の価値などというものより、今の今、自分の存在価値を、そのためになんとか生かしたいというのがぼくの望みだ。まさに、なだいなだ氏こそ真のモラリストで、生涯そのスタンスを貫き通した人だと感じました。
実のところ、この本は2020年2月5日に購入していました。
その後一度読み、本棚に並べられたままになっておりました。
最近のブーム(?)でか、当時も老後を扱った書籍が書店の売り場を占拠していて、わたしもご多分に漏れずその種の本を何冊か購入したことがありました。
その中の一冊がこの「とりあえず今日を生き、明日もまた 今日を生きよう」だった訳です。
一度読んでいるのですが、そのときは通読に近い浅い読みだったのかもしれません。
正直、あまり印象には残りませんでした。
老後をテーマにした作品では、多くのベテラン作家が自らの体験をもとに書いているのでしょうから、読者としては興味津々。
その上、自身の老後にも不安があれば、尚のこと両者の思いはシンクロしてこの分野の書籍は売り上げを伸ばすのは当然のこと。
当時のわたしはそんな背景に抵抗感があり、そうした先入観が読みの邪魔をしたのかもしれません。
「抵抗があるなら、買わなければ」と反論もあるでしょうが、わたしも一人の弱い人間、お許しください。
当時は、ブームの中の一冊としか捉えていなかったのだと思います。
作者の人生や生きてきた背景を知った上で改めて精読してみると、同じ作品でありながら、これほどまでに印象が異なるかを実感し、驚きました。
書籍に限らず、映画でも言えることですが、何年か経って「もう一度読みたくなる」、「もう一度観たくなる」作品こそ、乱暴な言い方かもしれませんが、優れた作品、つまり名作なのだと思います。
人生3分の2ほど経ってしまうと、遠い未来の輝いた理想よりも、今の今を噛みしめて生きることの方が価値があると思うようになるのですね。そんな思いを共有してくれる一冊です。
最後までお読みいただきあるがとうございました。
2022.04 JDA PROJECT
インフォメーション
- 2022.04 サイトをミニリニューアルしました。
- 2022.04 サイト名をLAULOA⇒LAULOA with HAWAIIに変更しました。
shop infoプロフィール
JDA PROJECT

人前ではいつも明るく、ひとりのときは思慮深く、ほどほどに芸術とハワイを愛し、いつも自然を大切に考え、焦ることなくマイペースで日々を過ごせたら、人生最高!
LINK
プラス得するハワイ情報サイ

ハワイ州観光局サイト

The Bus サイト